家族信託は、将来認知症になり、自身の財産管理が困難になるリスクに備え、家族や信頼できる人に財産管理を委ねる制度です。
財産管理を他者に託す方法は、家族信託以外にも複数あります。そのため、家族信託のメリットやデメリットを含め制度の仕組みをしっかり理解することが重要です。
記事のポイントは以下のとおりです。
- 家族信託とは、信託契約書に記載された内容に従い自己の財産管理を信頼できる人に委ねる制度です。
- 家族信託は柔軟に財産管理できるメリットがある反面、認知症後の契約や身上保護には不向きです。
- 資産凍結回避や障がいのある子への生活保障をしたい場合は、家族信託の活用をオススメします。
- 家族信託開始には契約書作成や信託口口座の開設、信託財産の名義変更が必要
- 銀行サービスにおける家族信託は通常と異なる仕組みなので注意
- 家族信託のメリットやデメリット、手続きや費用、活用例などの概要について解説します。
家族信託とは
家族信託とは、家族や信頼できる人に財産管理を委ねる手段です。これは「信託」の一形態であり、現在、“認知症による資産凍結”を防ぐ対策として注目されています。
高齢の親の財産管理における家族信託の場合は、委託者(親)が所有する財産(信託財産)を、信頼できる受託者(家族)に託し、その財産を受益者(親)のために管理してもらうことが一般的です。
一般的な家族信託では、親が子に財産管理を委ね、親が受益者となります。信託契約で、どの財産を子に管理させるか決定します。

家族信託の仕組み
前章のように財産管理をすることができる家族信託ですが、仕組みを理解するには、その主要な構成要素である「委託者」「受託者」「受益者」「信託財産」についてを知っておく必要があります。
家族信託は、財産管理や相続対策の手段として注目を集めていますが、実際の導入にあたって慎重な検討が必要となります。
本記事では、家族信託のデメリットと必要のないケースについて、専門家の視点から詳しく解説します。導入を検討する前に、14の注意点を理解し、自身の状況に本当に必要かどうかを慎重に判断することが重要です。
1)費用と経験豊富な専門家不足
- 手続きに費用がかかる
- 家族信託に詳しい実務家が少ない
- 法改正で契約が無効になるリスク
2)受託者を任せる家族の重大なリスク
- 受託者の負担や責任が重い
- 受託者の担い手がいない可能性
- 財産を勝手に使われるかも?受託者による権限の濫用
- 家族・親族間でトラブルになる
- 両親の同意をとるのが難しい
3)知らないと損する!制度上の重要な制限
- 途中での契約内容の変更ができない
- 家族信託では介護施設契約に対応できない
- 信託不動産の損益通算ができない
- 信託できない”対象外財産”がある
- 遺留分侵害額請求される可能性
- 直接節税対策にはならない
1)費用と経験豊富な専門家不足
家族信託の導入を検討する際、多くの方が気になるのが「費用」の問題です。しかし、実際には契約時の費用だけでなく、経験豊富な専門家が少ないことや、法改正による契約の見直しリスクなど、見落としがちな重大な問題点が存在します。
これから紹介するデメリットを解決するためには、豊富な実績を持つ専門家への相談が不可欠です。経験豊富な専門家は、過去の実績から起こりうる問題を予測し、それらを回避できる契約設計が可能です。また、法改正への対応力や、家族間の調整など、長期的な視点でのサポートも期待できます。

1. 手続き費用が高い
家族信託の導入費用は、成年後見制度など他の財産管理の仕組みと比べると高額になります。しかし、家族信託には大きな特徴があり、ご家族の状況や財産の特徴に合わせて完全オーダーメイドの対策を設計できる柔軟性が、メリットと言えます。
将来の財産管理を家族が自由に行える仕組み作りが可能になるので、その効果に見合った投資と言えるでしょう。
成年後見制度を利用した場合の費用と検討する
家族信託は最初の契約締結時点のみ費用がかかります。成年後見制度で、専門家が成年後見人へ選任された場合には、月額の報酬が継続的にかかる点と異なります。導入時に費用はかかりますが、長い目で見て成年後見制度と比較してみると家族信託のほうが安く済むケースがあります。
2. 家族信託に詳しい実務家が少ない
家族信託は2007年に制度が始まった比較的新しい仕組みです。そのため、豊富な実務経験を持つ専門家の数は極めて限られています。実は、「家族信託の相談可能」と謳う法律事務所でも、実際の経験が数件程度というケースも少なくはありません。
この専門家不足の問題は、単なる相談先の少なさだけでなく、より深刻な影響をもたらす可能性があります。経験不足の専門家が作成した信託契約は、将来の法改正や判例の変更に耐えられない可能性が高くなってしまうのです。
3. 法改正で契約が無効になるリスク
家族信託は、法制度としてまだ発展途上の段階です。そのため、法律の解釈や運用方法が年々変更されており、「グレーゾーン」が数多く存在します。実際に、2022年には相続空き家特例が使えなくなり、2024年には信託終了時の登記手続きルールが変わるなど、重要な解釈変更が続いています。
このような変更があると、いままでの信託契約の見直しが必要になったり、場合によっては契約内容の一部が無効となってしまう可能性があります。その結果、当初予定していた財産管理や運用ができなくなるリスクがあるのです。
事例①:相続空き家特例が家族信託では使えない
相続空き家特例とは、被相続人の空き家を相続して売却する際に、3,000万円の特別控除が受けられる制度です。しかし、2022年12月の税務当局の判断により、家族信託を利用している場合、この特例が使えないことが明らかになりました。
この変更の背景には、重要な法解釈の違いがあります。家族信託が終了した際の不動産の取得は、「相続または遺贈による取得」には該当しないと判断されたのです。この解釈変更により、これまで相続空き家特例が使えるものと思って作成した契約書の変更が必要になった事例です。
事例②:信託終了時の登記手続きの取り扱い
2024年1月までは、家族信託が終了する際の不動産登記手続きが非常に煩雑でした。特に問題だったのは以下の点です。
- 法務局によって手続き方法が異なる
- 相続人全員の印鑑証明が必要
- 相続人の協力が得られないと手続きが進まない
しかし、2024年1月からは受託者の単独申請が可能となり、手続きが大幅に簡素化されました。この変更により、相続人の協力が得られなくても、スムーズな名義変更が可能となりました。
2)受託者を任せる家族の重大なリスク
家族信託では、信頼できる家族に財産管理を任せることができます。しかし、受託者となる家族には想像以上の負担や責任が発生し、資産の使い込みなど権限濫用のリスクも潜んでいます。実際の運用では、家族間の信頼関係が崩壊するケースも少なくありません。
これから紹介する受託者に関するデメリットを解決するためには、適切な仕組みづくりが不可欠です。例えば、信託監督人の設置や複数受託者制の採用、定期的な報告義務の設定など、様々な対策が考えられます。特に重要なのは、ご家族の状況に合わせた最適な仕組みを設計することです。
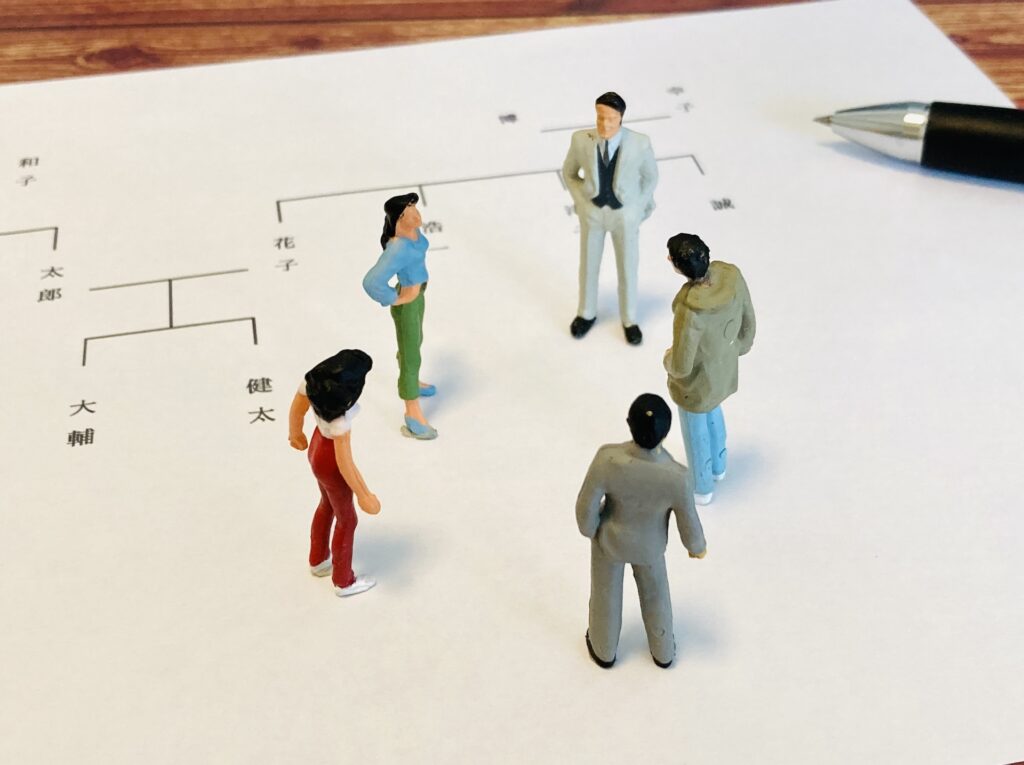
4. 受託者の負担や責任が重い
受託者は家族信託において重要な役割を担い、その責任と負担は重大です。しかし、この責任を適切に果たすことで、認知症になった親の財産を柔軟かつ自由に管理することが可能になり、家族の将来を守ることにつながります。
つまり、責任の重さに見合った権限が与えられることで、認知症などの将来リスクに備えた効果的な財産管理が実現できるのです。では、具体的な受託者の責任について見ていきましょう。
財産上の責任
万が一、信託財産で補えない損害が発生した場合、受託者は自身の財産で補填しなければならない「無限責任」を負うことになります。これは連帯保証人のような重い立場であり、受託者にとって、長期的な精神的プレッシャーです。
法律上の義務
受託者には以下のような厳格な義務が課されます。
- 信託事務の帳簿作成と管理
- 毎年の報告書作成
- 善管注意義務の遵守
- 利益相反行為の制限
家族関係への影響
財産管理の決定権を持つ受託者は、信託の運用に関する判断が難しい場合や、家族内で意見が対立する場合、受託者は心理的なストレスを感じることもあるでしょう。
5. 受託者の担い手がいない
家族信託は委託者と受託者の間の信託契約で成立しますが、その責任の重さから受託者の担い手が見つからないケースも少なくありません。受託者は財産管理の責任を負い、多岐にわたる業務を遂行しなければならないため、家族内で適任者を見つけることが難しいことがあります。
さらに難しいのが「後継受託者」の確保です。現在の受託者が万が一のときに備えて、信頼できる後継者を事前に決めておく必要があります。これが見つからないと、将来の財産管理が滞るリスクが生じます。
6. 財産を勝手に使われる?受託者の権限濫用
家族信託において、受託者は信託契約に基づき、委託者の財産管理や運用に広範な権限を持ちます。しかし、この権限は認知症になった親の財産を柔軟に管理するために必要不可欠ですが、同時に重大なリスクも伴います。
例えば、賃貸マンションを所有している場合、受託者は修繕や建て替えの判断、家賃の集金、入居者の選定など、契約書に書いた内容においてすべての権限を持ちます。この権限を悪用して、受託者が自分の都合で安価に物件を売却したり、知人を不当に入居させたりするといった濫用のリスクが考えられます。また、預貯金の管理においても、受託者の独断で高リスクな投資を行ったり、私的な目的で使用する可能性があります。
このような権限濫用のリスクを防ぐためには、信託契約の段階で適切な対策を講じることが重要となります。例えば、重要な財産処分には家族の同意を必要とする仕組みや、定期的な報告義務を設けること、さらには信託監督人を置くことで、受託者の権限を適切にコントロールすることができます。
7. 家族・親族間でトラブルになる
家族信託は、財産管理の有効な手段ですが、家族間の深刻な対立を引き起こすリスクがあります。
例えば、兄弟のうち1人が受託者となり、認知症の親の財産を管理することになったケースでは、遠方に住む弟が「事前の相談もなく決められた」ことに不満を持ち「勝手に父の財産を使っているのでは」と疑心暗鬼。こういった兄弟の関係が悪化するといったケースが考えられます。
このように家族信託でトラブルが発生する主な原因は、事前の説明や話し合いが不十分なことにあります。特に、財産管理の方針や受託者の選定過程が不透明な場合、他の家族は疎外感を感じやすくなります。さらに、定期的な報告や相談がないと、受託者への不信感が徐々に募っていき、取り返しのつかない家族関係の悪化を招くことがあります。
このようなトラブルを防ぐためには、家族信託の導入前に十分な話し合いを持ち、全員が納得できる仕組みを作ることが重要です。専門家のサポートを受けながら、透明性の高い財産管理の体制を整えることで、家族の絆を守ることができます。
8. 両親の同意をとるのが難しい
成年後見制度は本人が判断能力を失った後でも利用できますが、家族信託は違います。家族信託では本人が信託契約の当事者となるので、制度を利用する祖父母や両親の理解と同意が必要となります。これが得られない限り、家族信託を実行に移すことはできません。
家族信託は、「贈与」「売買」「遺言」などと比べて知名度が低いため、財産を預ける委託者にとって理解が難しいと感じられることがあります。また、不動産や金銭を本人ではなく受託者名義で管理するため、「難しそうだからやりたくない」「自分の財産が取り上げられるのではないか」といった不安感から同意を得られないことがあります。
家族信託の契約を進める際には、本人の理解と合意が必要です。家族信託の専門家の事例を踏まえた説明を取り入れることは、本人の誤解を解消し納得を促進する効果的な方法であると言えます。専門家を交えることで、本人の希望を取り入れた信託契約書を作成することができます。
3)知らないと損する!制度上の重要な制限
家族信託には、意外と知られていない重要な制限があります。介護施設との契約ができないこと、税金面での不利益、預貯金や年金が信託できないなど、制度上の制限により、期待していた効果が得られないケースが多く存在します。
これから紹介する制度上の制限は、適切な対策を講じることで回避や軽減が可能です。例えば、信託できない財産については代替手段の活用、税務上の不利益に対しては別の節税策との組み合わせなど、状況に応じた柔軟な対応が重要です。ただし、これらの対策には専門的な知識と経験が必要不可欠です。

9. 途中で契約内容の変更はできない
家族信託は、一度契約を結ぶと変更が難しい制度です。特に重要なデメリットは、委託者(親)が認知症になった後から、契約内容を変更することができなくなることです。
これは、家族信託が委託者と受託者の2者間の契約だからです。契約の変更には両者の有効な意思表示が必要ですが、委託者(親)が認知症になるとそれができなくなってしまいます。
そのため、契約内容は将来を見据えて慎重に検討する必要があります。例えば、介護費用の増加や不動産の修繕など、予想される支出に対応できる柔軟な条項を設定しておくことが重要です。また、契約時には医師の診断書を取得し、公正証書を作成するなど、契約の有効性を確保する対策も欠かせません。
10. 家族信託では介護施設契約はできない
家族信託は財産管理に限定された契約であり、信託された財産の範囲内での運用しか認められていません。つまり、委託者自身の財産や信託に含まれない財産の管理は対象外となるのです。
さらに、家族信託には成年後見制度で対応できる「身上監護」という役割が含まれていません。身上監護とは、医療施設の手続きやケアホームの入退所など、日常生活におけるサポートを指します。受託者が本人に近い子などであれば、施設が手続きを許可することもありますが、遠い親戚や無関係な第三者が受託者の場合、これらの手続きを行うのは難しくなってしまいます。
もし、医療施設の手続きなどが必要で身上監護をカバーする必要がある場合には、任意後見制度の併用をオススメします。任意後見制度を活用することで、任意後見人は被後見人の日常生活に関する法的行為を代行できます。家族信託と任意後見制度を併用することで、財産管理だけでなく、日常生活のサポートも包括的にカバーできるため、より安心して生活を送ることができます。
11. 信託不動産の損益通算ができない
家族信託を活用する際、特にアパートなどの収益物件を所有している場合には、損益通算の規定に注意が必要です。
家族信託では、個人の所得と信託不動産の所得を通算することができません。例えば、信託不動産が100万円の赤字で、委託者の個人所得が200万円の黒字だった場合、信託財産の赤字はなかったものと見なされ、200万円が課税対象となります。通常の青色申告では赤字を翌年以降に繰越して相殺できますが、家族信託ではこれも認められません。
収益不動産を家族信託する場合の注意点
収益不動産を家族信託する場合、この税務面での制限を考慮した対策が重要です。そのため、以下の対策が重要になります。
- 信託設定前に必要な大規模修繕を完了させる
- 複数の不動産がある場合、信託に組み入れる物件を慎重に選択する
- 必要に応じて任意後見制度との併用を検討する
これらの判断には専門的な知識が必要なため、経験豊富な専門家に相談することをオススメします。適切な計画を立てることで、将来の資産管理を円滑に進めることができます。
12. 信託できない“対象外財産”がある
家族信託は財産の管理を目的とした契約ですが、すべての財産を信託できるわけではありません。成年後見制度とは異なり、信託できない財産も存在します。以下に、間違いやすい信託財産についての留意点と対策を解説します。
預金口座
預金口座は信託契約書に口座番号を明記しても、直接信託財産とすることはできません。これは、預金口座の譲渡が基本的に禁止されているためです。対策として、信託したい金額を預金口座から引き出し、受託者名義の新しい口座に移すことで、間接的に信託財産として管理することが可能です。
年金
年金は受給者固有の権利であり、受託者名義の信託用管理口座に振込指定することはできません。対策として、年金を受け取った後、その金銭を受託者名義の口座に移し、追加信託として管理する方法があります。これにより、年金受給金も信託財産として取り扱うことができます。
農地
農地は農業委員会の許可や届け出がないと信託することができません。その対策として、まず農業委員会に許可や届け出を行う必要があります。専門家に相談して、必要な手続きを適切に進めることが重要です。宅地化を予定している場合も、同様の手続きを行うことで信託が可能になります。
借地権(土地の賃借権)
借地権は地主の許可が必要となります。信託契約には借地権の譲渡が含まれるため、地主の同意が求められます。対策として、借地権を信託する場合には、地主に信託の意図を説明し、理解と同意を得ることが必要です。専門家の助けを借りて、地主との円滑な交渉を行うことが大切です。
13. 遺留分侵害額請求される可能性
「遺留分」とは、配偶者、子、父母などの法定相続人に保障される最低限の相続財産のことです。これを侵すような家族信託契約を結ぶと、相続トラブルの火種となる可能性があるため、注意することが必要です。
遺留分に関する家族信託の取り扱いは、法的にはまだ確定していない部分が多くあります。2018年9月12日、東京地方裁判所では、遺留分を逃れる目的で結ばれた家族信託契約が公序良俗に反するとして一部無効とする判例が出されました。最高裁での最終的な判断はまだ出ていないため、今後の法的動向に注視する必要があります。
遺留分も踏まえた対策
遺留分を考慮し、相続人全員が納得できる信託契約を設計することが重要なので、専門家の助言を受けながら契約内容を慎重に検討し、トラブルを未然に防ぐ対策を講じましょう。また、家族信託を介さずに財産を受け継ぐ予定の相続人には、遺言や生命保険を活用して財産の承継を確保することも考慮する必要があります。これにより、遺留分侵害を回避しつつ、円滑な相続を実現できます。
14. 直接節税対策にはならない
「家族信託を利用すれば相続税が軽減される」との誤解が広がっていることが背景にありますが、家族信託は、直接的な相続税の節税手段ではありません。
家族信託を行っても、財産の実質的所有者は依然として本人です。そのため、相続税の評価は変わりません。財産を任された受託者は名義上の管理者として行動できるようになりますが、財産権や受益権は本人に残るため、信託を利用しただけでは相続税の評価を下げたり、節税効果を得ることはできません。
長期にわたる受託者の対策による間接的な効果
家族信託を長期にわたってうまく活用することで、次のような間接的な効果が期待できます。
- 委託者が判断能力を失っても、受託者が相続対策を進めることができる。
- 本人他界後も家族信託を続けることで、二次相続対策も行える。
これらの効果は、家族信託を長期的かつ適切に活用した結果として得られるものです。家族信託自体には直接的な節税効果はないことを理解し、他の相続税対策と併用することが重要となります。
家族信託が必要ないケースとは?
家族信託は、財産管理の有効な手段として注目されている一方、すべての方に適しているわけではありません。これまで解説してきた14のデメリットを踏まえると、むしろ家族信託を避けるべきケースも存在します。
家族信託の導入を検討する前に、本当にご自身のケースに必要かどうかの判断が重要となります。例えば、家族間に争いがある場合や、信頼できる受託者が見つからない場合に家族信託を選択すると、かえってトラブルのリスクが高まる可能性があります。また、委託者が若く健康な場合や、財産管理のニーズが限定的な場合は、他の方法で十分対応できるかもしれません。

このような判断には、豊富な経験に基づく専門的な視点が必要ですが、この章では6つのケースにわけてご紹介していきます。
家族信託は「生前の遺産分割に近い」と説明されることが多く、将来の財産管理と資産承継先を生前に家族会議を経て決めておくことで、その後のトラブルを防ぐことが期待されています。しかし、「事前に説明ができない」「家族関係に問題がある」といったコミュニケーションに問題がある状況では、家族信託が逆にトラブルの原因となる可能性があります。
例えば、次のような場合には家族信託を避けた方が良いかもしれません。
- 家族の仲が悪い
- 親族同士で話し合いができない
- 一部の家族が信託契約に納得していない
このような場合、家庭裁判所の関与の元で中立な第三者が成年後見人として管理する成年後見制度を利用する方が安全です。また、家族間で財産管理の権限を持つ人に対する不公平感が生じることもあります。
家族信託をした場合に想定されるトラブル
家族信託契約は委託者と受託者の同意があれば成立するので、他の家族の同意は法律上必要ありません。しかし、実際には家族全員が納得しなければ、裁判沙汰や日常生活での小競り合いが続く可能性があり、次のようなトラブルが考えられます。
- 判断力が鈍った親(委託者)を騙して無理やり結んだのではないかと疑われる
- 「なぜ、他の家族に話を通さずに勝手に受託者を決めたのか」と周りから権力の集中について非難される
- 「自分は兄よりうまく財産を扱えるはずだ」といった受託者選定に関する不満が他の家族から出る
- 家族信託を任せた子ども(受託者)が財産を不正利用して暴走しているが周囲に止める権限がない
- 受託者として常に大きな権限と義務を持ったが周りにサポートしてくれる人がいない など
親の財産を一人の子が独占して管理し、外部に情報開示しないような家族信託は、将来の「争族問題」を引き起こす可能性があります。将来の相続人全員が納得していない場合は、家族信託を慎重に検討することが、とても重要です。
ケース1 受託者を任せられる親族がいない
家族信託を結ぶ際、受託者となる親族には非常に広い権限が与えられます。信託財産の管理、運用、処分だけでなく、信託契約に基づいた行為も基本的には可能となります。その一方で負担や義務が重く、家族信託は「受託者を誰にするか?」が非常に重要な制度です。
受託者には、自分の財産と信託財産を別々に管理する「善管注意義務」が課されます。これは、他人の財産を預かり管理するという責任を非常に高いレベルで遂行することを求められるものです。親族であっても、信託財産を自分のもの以上に注意深く管理する能力と意識が必要です。
こうした責任を果たせる親族がいない場合、家族信託を結ぶのは難しいかもしれません。その場合は、信頼できる専門家に成年後見人となってもらい、財産管理を任せる方が安心確実でしょう。専門家であれば、法的な知識や経験を活かし、適切に財産を管理・運用することが期待できます。
また、受託者の負担を軽減するために、信託監督人や受益者代理人を設ける方法もあります。これにより、受託者一人に過度な負担がかからず、家族全体で信託をサポートする体制を整えることができます。しかし、それでもなお、受託者となる親族の信頼性が確保できない場合は、専門家の力を借りるのが最善です。
ケース2 委託者が若く認知症ではない
若くて健康状態が良く、認知症のリスクが低い場合、家族信託はまだ必要ないことがあります。健康な状態であれば、生前贈与や不動産の売却など、他にも多くの生前対策の方法があります。また、万が一に備えて遺言を作成しておく程度の対策で十分でしょう。これにより、財産の管理や相続に関する基本的な準備は整います。
ただし、健康状態に変化の兆候が見られた場合には、家族信託の導入を検討するべきです。一般的には、65歳を超えた段階から家族信託の検討を始めると良いでしょう。健康であるうちに適切な対策を考えておくことで、将来的なリスクに備えることができます。
ケース3 親の不動産売却や施設費用を支払う予定がない
家族信託のメリットは、信託財産について契約の範囲内で管理・運用しやすくなる点です。つまり信託財産による収益の見込みがなかったり、そもそも不動産といった収益性がある財産を持っていなかったりする場合は、家族信託を結ぶ必要がない可能性があります。
例えば下記のケースです。
- 委託者の自宅や所有するアパートの貸付・売却などの予定がない
- 親の認知症によって凍結される財産がない、もしくは凍結しても困らない
- 親の介護や治療、生活、施設への入居などの出費に関して信託財産の収益を当てにしていない
- 相続に関しては遺言で十分に対応できる など
ケース4 生前贈与などで資産譲渡が完了している
例えば、生前贈与によって受託者にしたい人への財産譲渡や名義変更がすでに完了している場合、あるいはその予定がある場合は、家族信託を新たに結ぶ必要はありません。
家族信託と生前贈与、それぞれには独自のメリットとデメリットがあるため、状況に応じて選択することが重要です。なお、家族信託と生前贈与のどちらも、一方が認知症やそのほかの病気などで判断能力がなくなると契約を締結できません。
| 家族信託 | 生前贈与 | |
|---|---|---|
| 財産の管理 | 受託者 委任者(受益者)が受託者へ意見できる | 贈与された者 贈与した側の意見に関係なく財産を管理できる |
| かかる税金 | 贈与税(※) 相続税 登録免許税(家屋評価額0.4%) | 贈与税 不動産取得税 登録免許税(家屋評価額2%) |
| 契約終了の条件 | 家族信託契約の終了 | 贈与した側への再贈与や売買 |
| 詳しい専門家 | 少ない | 多い |
※ 委託者と受益者が違う人物であるとき(他益信託)は課せられる可能性がある
ケース5 資産より身の回りの管理をしてほしい
家族信託で管理できるのは信託財産に関わる範囲に限られます。例えば、認知症になった方の介護や治療、生活、施設への入居などの契約や法律行為は代行できません。こうしたケースに対応できるのは、「身上監護」がついている成年後見制度(法定後見制度と任意後見制度)になります。
もし、親の認知症対策で「お金や不動産だけでなく、毎日の生活や介護関係などに関する法手続きを自分で行いたい、もしくは信頼ある人に任せたい」という場合は、成年後見制度の利用も検討しましょう。とはいえ多くの介護・医療施設では身上監護がなくても、サービスを受ける本人の家族で近くに住んでいるときは手続きの代行を認めています。
ケース6 信託できない財産が多い
家族信託を検討する際には、自分の持っている財産が信託財産にできるかどうかを確認することが重要です。実は、信託できない、もしくは信託するのが難しい財産があります。
デメリット12(信託できない“対象外財産”がある)でも解説していますが、農地や年金は信託財産とすることができないため、例えば年金だけで生活している方などは家族信託ではなく、成年後見制度の利用をオススメします。
家族信託をすべきケースとは?
これまでに多くの家族信託のデメリットを見てきましたが、それでも家族信託を検討すべきケースが存在します。家族信託は、特定の状況下で非常に有効な財産管理手段です。以下では、家族信託が特に有用であり、検討すべきケースについて詳しく説明していきます。
家族だけで財産を柔軟に管理したいケース
家族だけで財産を柔軟に管理したい場合、家族信託は非常に有効な手段とです。成年後見制度では、家庭裁判所が関与し、専門家が後見人として選ばれることが一般的となります。後見人が財産管理を行う場合、財産の売買や大規模な修繕などの重要な決定には、家庭裁判所の許可が必要です。
一方、家族信託を利用すれば、家族内の信頼できる人に財産管理を任せ、信託契約に基づいて財産の管理・運用・処分を行うため、家庭裁判所の許可を待つことなく迅速に対応できます。
さらに、家族信託では信託財産の使い道を詳細に規定することができるため、家族のニーズに合わせた柔軟な財産管理が可能です。例えば、生活費や医療費の支払い、特定の教育資金の確保など、家族の状況に応じた管理ができます。
孫世代の相続や引き継ぎたい財産がある
通常の遺言や生前贈与では、一次相続人(子供や配偶者)に対しては財産の引き継ぎは可能ですが、その後の二次相続については指定できません。つまり、一度財産を受け取った人が亡くなった後、その財産が誰に渡るかを事前に決めることができません。
もし、子供や配偶者の後、相続させたい相手がいる場合には、家族信託は非常に有効な手段となります。家族信託の「受益者連続型信託」を利用することで、子供や配偶者だけでなく、孫やひ孫といった複数世代への相続先を指定することができます。これにより、委託者は自身の財産が直系の家族だけでなく、将来の世代にも確実に継承されるよう指定することができるのです。
代々継いでいってほしい土地や財産についての相続先を決められるのは、家族信託が備える有効な機能の一つです。ご家庭でそういった要望がある場合は家族信託を検討したほうがいいと思われます。
共有不動産による管理を楽にしたい
兄弟姉妹などが共同で所有する不動産を持っている場合、管理や売却などの手続きにも全員の同意が必要になります。特に一人でも意思決定能力が欠けてしまうと、管理や売却などの手続きをすることが困難になり、資産凍結のリスクにつながってしまいます。
家族信託は、委託者から受託者に管理権限を委託することができる制度です。家族信託を活用し、特定の代表者(受託者)に不動産の管理や運営の決定権を集中させておくことにより、共有者が認知症になっても手続きが停滞することなく進められます。さらに、受託者が管理する不動産から得られる収益は、信託契約に基づき、他の共有者にも公平に分配されるため、全員の利益を守ることが可能になります。
事業承継を円滑にしたい
家族信託は、金銭や不動産だけでなく、事業関連財産の管理にも利用できるため、事業承継を円滑に進めるための強力なツールとなります。
例えば、創業オーナーが持つ自社株式を信託財産として設定することで、事業の継続性を確保しながら、スムーズな株式の承継や事業継承計画を立てることが可能です。委託者が認知症などで意思疎通が難しくなった場合でも、受託者が経営決定権を持続的に行使できるため、事業の安定性を保つことができます。
家族信託は、経営者の意向に沿った事業の継承を実現するための有力な選択肢となります。事業承継計画を立てる際には、家族信託の利用を検討し、専門家のアドバイスを受けながら最適な方法を選択しましょう。

